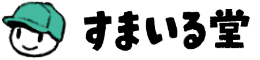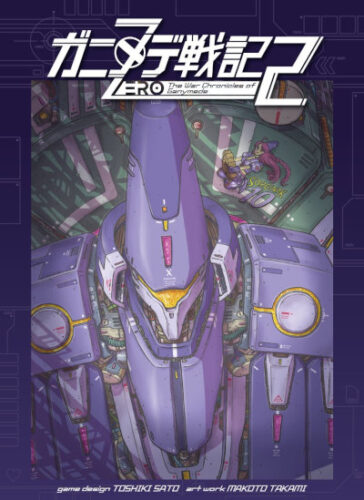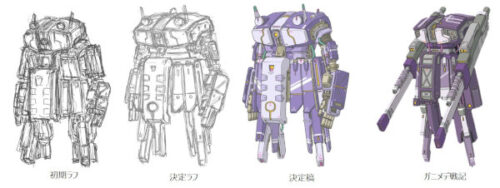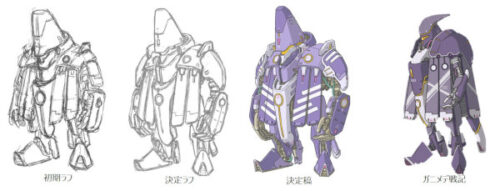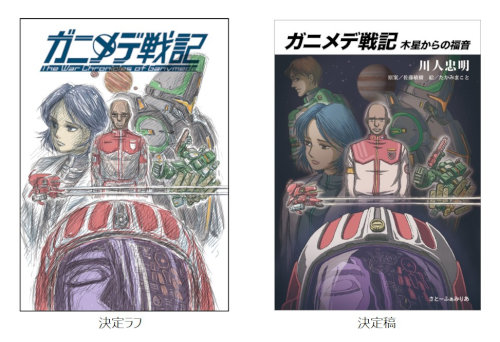キスまでの階段 α版2023.05.13

ゲーム概要
恋人同士がキスをするまでには、いくつかのステップがあります。
どのようなステップを踏むかは恋人次第。
素敵なキスを重ねていきましょう。
ゲーム情報
![]() プレイ人数:2~5人
プレイ人数:2~5人
![]() プレイ時間:10分
プレイ時間:10分
![]() 対象年齢:12歳以上
対象年齢:12歳以上
ルール
内容物
・カード:36枚(1-9:各4枚)
・説明書:1枚
・チップ:白10枚、黒20枚
(チップはご自分でご用意ください。チップの代わりに紙とペンでもOKです)
概要
このゲームは手札を使い切る(アガる)ことを目指すゲームです。
アガることができれば白いチップを獲得します。
手札を受け取ってから、いずれかのプレイヤーがアガるまでを1シーズンと呼びます。
シーズン終了時に手札が多いと黒いチップを受け取ります。
誰かが黒いチップを3枚受け取ったときに、白いチップが多い人の勝利です。
準備
(1) すべてのカードを裏向きにして混ぜ、裏向きのまま1つの山札を作ります。
(2) 各プレイヤーは山札から5枚ずつカードを引き、手札にして、自分だけがカードの内容を確認します。
(3) スタートプレイヤーを決めます。スタートプレイヤーは最近階段をのぼった人です。もしくはじゃんけん等で決めてください。
※(3)は最初のみ
流れ
(1) スタートプレイヤーは好きなカードを1枚手札から表向きにして場に出します。
(2) 左隣のプレイヤーは場に出されているカードより、1だけ大きいカード1枚を表向きにして場に出します。
出せない場合もしくは出したくない場合は、山札からカードを1枚引いて手札に加え、パスします。引いたカードはすぐには出せません。
山札がない場合、山札からカードを引きません。この場合はパスをするのみです。
パスした後、他のプレイヤーがカードを出した場合、パスしたプレイヤーもカードを出すことができます(ソフトパス)。
(3) カードを出したプレイヤー以外の全員が連続でパスをしたら、場にあるカードを
すべて流します(ゲームから除外します)。
最後にカードを出したプレイヤーから(1)を行います。
(4) 出したカードが9だった場合、場にあるカードをすべて流します(ゲームから除外します)。
9のカードを出したプレイヤーから(1)を行います。
(5) 誰か一人のプレイヤーが手札を使い切ったらアガりです。
アガったプレイヤーは白いチップを1枚受け取ります。
その時、一番多くの手札を持っていたプレイヤーは黒いチップを1枚受け取ります。
最多の枚数の手札を持っているプレイヤーが複数いる場合は、最多の枚数の手札を持っている全員が黒いチップを1枚受け取ります。
今のシーズンでアガったプレイヤーを次のシーズンのスタートプレイヤーにして、次のシーズンを「準備」から始めます。
終了条件
いずれかのプレイヤーが黒いチップを3枚受け取ったら、ゲーム終了です。
黒いチップを3枚受け取ったプレイヤーはゲームから脱落します。
脱落していないプレイヤーの中で、もっとも多くの白いチップを持っているプレイヤーが勝ちです。
白いチップの枚数が同じ場合はそのプレイヤーの中で黒いチップが少ないプレイヤーの勝ちです。
それでも勝負がつかないときは勝利を分かちあいましょう。
クレジット
![]() ゲームデザイン:佐藤敏樹
ゲームデザイン:佐藤敏樹
![]() イラスト:ツクダヒナミ
イラスト:ツクダヒナミ
![]() スペシャルサンクス:高橋幸子先生、ぽてさん
スペシャルサンクス:高橋幸子先生、ぽてさん
![]() 発表:α版 2023年5月13日
発表:α版 2023年5月13日
参考ゲーム
![]() ページワン
ページワン
![]() ニューマーケット(トランプゲーム)
ニューマーケット(トランプゲーム)
![]() ラマ
ラマ
デザイナーズノート
とっかかり
今年長女が中学受験をしたのですが、その入試の待ち時間、その学校の図書室で何気なく手に取った雑誌に「交際の12段階」が紹介されていました。
これは産婦人科医の高橋幸子先生が提案されているもので、交際には段階があるというものです。
1段階目の「目と目が合う」から始まり、「言葉を交わす」「並んで歩く」という具合にだんだんと親密度が増していきます。
12段階目は「性器の挿入を伴う性行為」となっているのですが、昇順に並んでいることに「ロストシティ」のようなゲーム性を感じました。
このリアルな段階が楽しく、みんなで遊んだら面白そうと思い、ゲームとして開発することを決めました。
テーマ的に段階を大きく飛ばさない(数字を飛ばさない)方がいいだろうと考え、いろいろなルールを試していきました。
イラストについて
ある日、歩きながらこのゲームに合うイラストを考えていました。
そして、思いついたのがツクダヒナミさんです。彼女のイラストの雰囲気と恋愛テーマが非常にマッチすると思いました。
ツクダヒナミさんの絵を思い付いたときは「これしかない!」と叫びたい気分でした。
実際、Twitterに何やら興奮した口調でつぶやいていました。
出すべきか出さざるべきか
しかし、このテーマをゲームとして売る機会はあるのか、非常に悩ましい問題でした。
何せ12段階目は「性器の挿入を伴う性行為」ですから。
そこで「交際の12段階」を提案されている髙橋先生に直接連絡を取りました。
12段階目を「身体を重ねる」とオブラートに包んでもいいですかと。
その回答は「ダメ」でした。ここは濁してはしてはいけないという先生の信念でした。
同時に14歳の息子とテストプレイをした時も、「パパ、このゲームは出せないよ」という反応で、八方塞りになりました。
でも、息子がアドバイスをくれました。「9段階目のキスまではいいけど、10~12はダメだと思うよ」
それを聞いて「ゲームのゴールを9段階目までにすればいいんだ。これならゲームとして出せる!」と思いつきました。
ルールの確定
ただ、しっくりくるルールが思いつきません。ある日、草場さんがNHKに出ていると聞き、テレビをつけました。テレビでは楽しそうにページワンを遊んでました。そのときです、トランプゲームくらいのシンプルさでいいのかもと閃きました。
それから急いでトランプ大全をひっくり返し、相性のよさそうなゲームを探しました。そして、「ニューマーケット」をベースに『キスまでの階段』のルールを作り上げました。
ゲムマチャレンジ?
ルールを作る上でコンポーネントの調整をしていると、1~9のカード4枚ずつがバランスが良さそうと気づきました。そしてまた閃きました。「これならレギュレーションの変わったゲムマチャレンジに参加できるかも」
カード36枚というゲムマチャレンジは今年のみ。ならば是非作ってみようと思い立ち、印刷所の締め切りを確認したり、イラストのツクダヒナミさんと入稿の調整をしたり、りかちさんにゲムマチャレンジガチャの申し込みをしたりしました。
しかし、1週間後にゲムマチャレンジのレギュレーションが変更されました。36枚ではなく32枚までという変更でした。
キスまでの階段を減らすわけにはいかないので、32枚に削ることは困難です。
ゲムマチャレンジはあきらめましたが、ゲムマ春にお試し版として販売することに決めました。
入稿完了
なんとか原稿が間に合いました。
「入稿予定日の26時までには送ります!」と言ってたツクダさんからは翌朝6時を過ぎても連絡がなく、お昼過ぎにDMしたところ「メールした気でいました!」というハプニングもちょっとありましたが、なんとか入稿しました。
印刷があがったはの5月7日のゴールデンウィーク最終日。家で丁合をして、なんとか試作販売分の準備ができました。
今後の予定
10部は自分のブースで販売し、残りはりかちさんのゲムマチャレンジガチャに委託しました。
来年には正式版として販売する予定です。「あそんだよー」など、気軽にツイートいただけると幸いです。